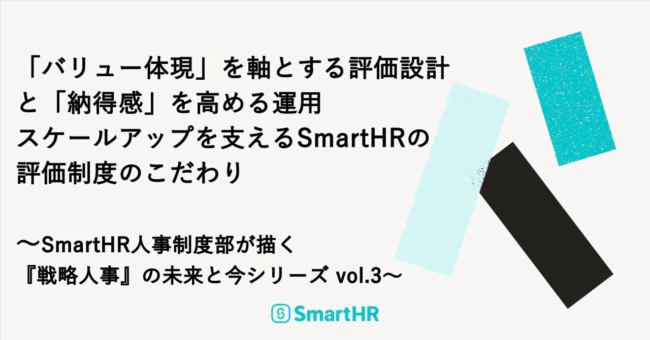SmartHR社の評価制度について、一部寄稿しました。
シリーズ化されていますので、そちらの記事も。
- 企業成長を加速させる人事制度と、それを生み出す組織のあり方とは? 〜SmartHR人事制度部が描く『戦略人事』の未来と今シリーズ vol.1〜
- 転職して1年、ぶっちゃけどうですか?SmartHR人事制度部で働く2人のリアル 〜SmartHR人事制度部が描く『戦略人事』の未来と今シリーズ vol.2〜
人事制度部の企画・設計・運用のリアルが伝わってくる意義のある記事だと思います。
SmartHR社の評価制度は、バリューそのものや評価尺度、評価の名称は変われど、基本的な構造は2016年に設計したものがベースになっています。
当時20名弱の方々を対象に行っていた評価制度が、1000名以上の方々に適用されています。
もうすぐ10年の運用になりますが、その過程では数えきれないほどの振り返りと改善を行ってきました。
この経験値が組織能力へと転化し、人事制度部にもしっかりと伝承されていると思います。
もはやスタートアップというフェーズではない会社ではありますが、絶え間ないチューニングを即断・即決・即実行してきた文化こそ、他社がマネできない競争優位の源泉です。
制度設計の補足
さて、バリューや行動指針を反映した定性評価について、気をつけたいポイントを1つ。
等級要件を評価基準に反映するのは、NGです。
当たり前と思われるかもしれませんが、自分の経験上、スタートアップで人事制度(特に評価制度)がうまく機能していないケースで最も多い原因です。
根本原因は、人事制度において等級制度と評価制度の切り分けができていないということ。
等級制度と評価制度の違いについて、自分の言葉でしっかりと説明できることが重要です。
等級要件は、会社の期待であり、成長の指針。
土台となる全社一律の等級要件は、抽象的になります。
これを機械的に自己評価・メイン評価しても、意味のある振り返りにはなりません。
評価基準は、日々の判断・行動の基準です。
具体的に設計(言語化)しないと、実践に堪えません。
評価基準のまま、理解できる・振り返れる・フィードバックできる状態まで言葉を磨く必要があります。
この部分に設計者としての技術や経験が現れます。