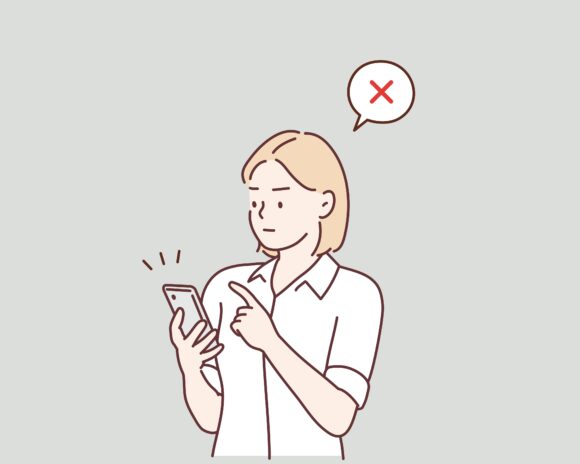パフォーマンスとプロセスの2軸で評価する際、プロセスの評価基準として自社のバリューを使うことがあります。
そのとき、どこまでバリューを具体化するか、で悩まれることをよく耳にします。
私が設計する際に心がけていることは、等級別には具体化しない、です。
まずは「Do/Don’t」から言語化する
バリューを具体化する際によく使われるのが「Do/Don’t」です。
バリューを具体的な行動基準(もしくは判断基準)に落とし込むのに、良いケースと良くないケースを言語化するという意味です。
バリューとは価値観であり、抽象度が高いゆえ、具体的な行動や判断の基準に落とし込まないと、読み手である社員は当惑してしまいます。
このバリューはどういう行動や判断を期待しているのか、そしてそれはなぜか?まで言語化することが理想です。
この作業は、クリエイティブな作業です。
だれにでもできるものではありません。
経験と技術を必要とする特殊技能だと思う必要があります。
なぜなら、この基準を言語化することで、相手の行動や納得を引き出し、その結果として成果まで繋げることができるためです。
人事ではなく、経営が責任を持って対応しましょう。
等級別に具体化しない
「Do/Don’t」を具体化し、運用し始めると、それでも現場からは「もっと具体的にしてほしい」という声が挙がります。
そのとき、「等級別に基準をつくるのがいいのでは?」というアイデアから沼にハマっていくことがあります。
実際、等級別につくろうとすると「3等級と4等級の違いがわからない」や「違いを設けたけど、無理くりつくっている感じがする」、「5等級の基準より4等級の基準の方が難易度が高いのでは?」、「あの人5等級だけど、3等級の基準ができていないのでは?(それってそもそもいいの?」といった制度に対する様々な意見が出てきます。
何のためにバリューを評価基準に組み込んだのか、という本質的な背景を見失い、言葉遊びに対する知的討論が起きる感覚です。
こういう抽象的な制度や基準は、正直、なんか文句つけようと思えば、いくらでもできますが、その先にあるものは進化や成果ではなく、無駄と不信です。
バリューを評価基準に組み込む際、等級別に詳細化する必要はありません。
理由は、バリューの評価基準は等級が違えど大きく変わらないからです。
では、何が変わるのか。
被評価者の「仕事内容」です。
つまり、3等級の方が担う仕事と5等級の方が担う仕事は、その難易度や影響度が違います。
その仕事に対して、同じ意味合いのバリューを体現していくのです。
だから、仕事の難易度や影響度は変わるけど、バリューの体現の仕方は変わりません。
これを理解せずに、バリューを等級別に精緻化してしまうと、様々な職種に応じた仕事内容にフィットしない基準が出てきてしまい、制度が機能しなくなってしまいます。
バリューは等級別に具体化するのは、筋のよい打ち手ではありません。
職種別に「Do/Don’t」を具体化するのは有り
等級別に具体化しない一方で、職種別に具体化するのは有りです。
すべての職種で具体化することを必須とはせず、必要な職種のみ具体化します。
被評価者や評価者の数が多い職種は、具体化のニーズは高めです。
職種別に具体化するのは、等級別と違って上下の難易度や整合性を気にする必要がありません。
他の職種には、正直、内容の是非も分からないため、その職種の責任者を信頼して任せることになります。
職種別のバリューの評価基準は、あくまでもオプションです。
設計に急ぐことはなく、現場から「必要」との声が挙がってきたタイミングで、着手しましょう。
声が挙がることに対して、ナーバスになる必要はありません。
課題が見えてきたところで対応できれば、十分に間に合います。